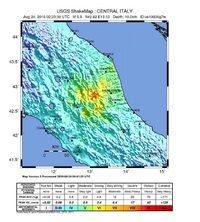2016年08月15日
資源管理という概念で活断層地震対策を公共的に行う
佛念寺山断層による地震の懸念に関して、社会的にどういう風に対応していくのかという疑問があり、WEBめぐりでいろいろな文献を参照してみました。今回は2005年の日本地理学会の予稿からの引用です。
ニュージーランドには防災・都市計画等を含む環境行政全般に関する資源管理法があり、活断層上の土地利用を自治体が規制している例があります。
(2005年度日本地理学会春季学術大会 予稿P 268「ニュージーランドの活断層上と近傍の開発計画指針」村山 良之, 増田 聡, 梅津 洋輔。東北大学を参照しました)
2003年、ニュージーランド環境省は、「活断層上と近傍の土地開発計画」のための暫定的ガイドラインを公表しています。(2004, 都市計画論文集,39)
ガイドラインにおいては、都市計画に以下の4原則を提案しています。
1) 正確な活断層ハザード情報の収集と都市計画図への記載:最低縮尺1/1万の都市計画図に活断層の地図化が必要。
2) 新規開発・分譲に先立つ断層破壊ハザード回避策の計画:例えば断層破壊地区での建築制限。
3) 既成開発・分譲地でのリスク・ベースト・アプローチの採用:リスク管理規格AS/NZS4360:1999による。建物被災回避を完全には保証しないが、一般に受容可能な低リスクに抑える。
4) 既成市街地内の断層破壊地区におけるリスク・コミュニケーションの促進:現状を容認しつつ、次期開発や建物利用をリスクレベルに見合ったものにする。教育プログラムや移転奨励策等の非規制的アプローチを含む。
次に目を転じて、日本の法律に基づく規制を見ると、災害危険区域(津波、高潮、出水等の危険区域を指定し、建築の禁止や制限。)、宅地造成工事規制区域(宅地造成に伴い災害のおそれある場合に指定。)、防火地域・準防火地域(市街地での火災の危険地域を指定。建築物構造の難燃化。木造家屋の立地制限。)などがあります。さらにまた、都市計画法の市街化区域・市街化調整区域でも、津波、高潮、出水等の恐れのある土地等は、防災上具体的措置なしに市街化区域には含めないとなっています。
しかし、こうした法制・規制の中には活断層のよる地震のような災害に関して具体的な言及なく、活断層による地盤変動による危険を予防する危険区域の認定や、規制などに関してはまだ、一部の自治体の条例制定にとどまっているといえましょう。100年スパン、1000年スパンで発生する地震に関しては発生し、被災することは確率論的にも低い数字となり、まだ、手が打たれていない状況かと思います。しかし、阪神大震災、東北震災、熊本地震と日本国での発生頻度を考えると、できるところから手を打たねば折角蓄積してきた日本の文明がズタズタになってしまいます。
ニュージーランドには防災・都市計画等を含む環境行政全般に関する資源管理法があり、活断層上の土地利用を自治体が規制している例があります。
(2005年度日本地理学会春季学術大会 予稿P 268「ニュージーランドの活断層上と近傍の開発計画指針」村山 良之, 増田 聡, 梅津 洋輔。東北大学を参照しました)
2003年、ニュージーランド環境省は、「活断層上と近傍の土地開発計画」のための暫定的ガイドラインを公表しています。(2004, 都市計画論文集,39)
ガイドラインにおいては、都市計画に以下の4原則を提案しています。
1) 正確な活断層ハザード情報の収集と都市計画図への記載:最低縮尺1/1万の都市計画図に活断層の地図化が必要。
2) 新規開発・分譲に先立つ断層破壊ハザード回避策の計画:例えば断層破壊地区での建築制限。
3) 既成開発・分譲地でのリスク・ベースト・アプローチの採用:リスク管理規格AS/NZS4360:1999による。建物被災回避を完全には保証しないが、一般に受容可能な低リスクに抑える。
4) 既成市街地内の断層破壊地区におけるリスク・コミュニケーションの促進:現状を容認しつつ、次期開発や建物利用をリスクレベルに見合ったものにする。教育プログラムや移転奨励策等の非規制的アプローチを含む。
次に目を転じて、日本の法律に基づく規制を見ると、災害危険区域(津波、高潮、出水等の危険区域を指定し、建築の禁止や制限。)、宅地造成工事規制区域(宅地造成に伴い災害のおそれある場合に指定。)、防火地域・準防火地域(市街地での火災の危険地域を指定。建築物構造の難燃化。木造家屋の立地制限。)などがあります。さらにまた、都市計画法の市街化区域・市街化調整区域でも、津波、高潮、出水等の恐れのある土地等は、防災上具体的措置なしに市街化区域には含めないとなっています。
しかし、こうした法制・規制の中には活断層のよる地震のような災害に関して具体的な言及なく、活断層による地盤変動による危険を予防する危険区域の認定や、規制などに関してはまだ、一部の自治体の条例制定にとどまっているといえましょう。100年スパン、1000年スパンで発生する地震に関しては発生し、被災することは確率論的にも低い数字となり、まだ、手が打たれていない状況かと思います。しかし、阪神大震災、東北震災、熊本地震と日本国での発生頻度を考えると、できるところから手を打たねば折角蓄積してきた日本の文明がズタズタになってしまいます。
Posted by nobcha at 19:49│Comments(0)
│大都市直下断層
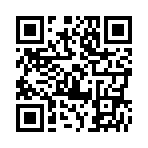
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン